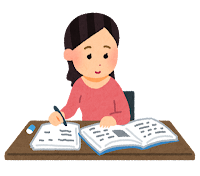鈴木修塾では、塾開催日のおおよそ1~2ヶ月前くらいから参加者全員とLINEグループを作って、事前の研修を行います。
1月31日から始まる鈴木修塾(土地家屋調査士事務所開業・経営)については、受講申込みの締切り前ですが、既に参加を申込みいただいた人たちについてはLINEグループによる研修も始めていますし、個別にも電話等で指導も始めています。
さて今回の塾の受講生Oさんと電話していて、「何から勉強したら良いか分からない」との相談がありましたので、現在Oさんが持っている書籍類の写真を送ってもらいました。
それらを見ると、あまりにも読書量が不足していることがわかりました。
それはOさんだけではありません。たいていの新人は読書量が圧倒的に不足しています。
そこで、彼にしたアドバイスの趣旨をここで紹介します。
資格試験が終わったばかりだから、不動産登記法や民法の書籍は受験本しか持っていないのでしょう。実はそれらは受験の本であって、法律全体を理解する本ではありません。
試験に出る部分をクローズアップしているので、法律の流れや考え方が偏ってしまう可能性があります。もちろんそれらの本は悪い本ではありません。目的が違うだけです。
それらの本は、受験本として優れているから皆さんも合格したのでしょうから、感謝して本棚にしまいましょう。
試験合格したから、Oさんは不動産登記法と民法はマスターしているつもりなのでしょうけれど、土地家屋調査士の資格試験の合格レベルだとすれば、それは実務に対応できる法律レベルではないのです。
しかもOさんが、もし受験後に勉強を休んでいたら、そのレベルすら怪しくなっていますよね。
もちろん大丈夫です。ここから鍛え始めれば良いだけです。これからが本番の勉強です。
塾で会うまでに、常に勉強する習慣に戻してもらいたいと考えています。
プロを目指すのなら、不動産登記法や民法は卒業ではなく、ここから深掘りしなければならないのです。
でも、専門書でも尖った部分の書籍も少し早いと思います。深掘りするためにも基本からしっかり学び直して欲しいです。基本がわからないのに難しい技を覚えようとすると、消化不良のまま悪い癖がつきますので。
塾では皆さんそれぞれとお話をして、皆さんそれぞれの背景や能力にあった本を推薦しています。Oさんともいろいろお話しして推薦したいと思います。
また、これから本を読むときは、暗記することを目的にしないようにしてください。
私達は、小学校から資格試験まで「試験問題に対する答えを出す」という勉強をしてきましたが、プロの現場では暗記は不要です。プロの現場では常に隣に六法がありますから。
読み方としては、書いてあることをひたすら暗記するのではなく、何故そう考えるのかを理解してください。
その法律全体では「何が幹で何が枝葉なのか」を理解するようにしてください。
試験問題は枝葉から出るので、それに慣れすぎている受験生は文字どおり枝葉末節な議論しかできなくなります。とにかく大きな法律の流れを把握するように勉強してください。
Oさんをはじめとする合格者の皆さんのプライドをけなすつもりは無いのですが、一度そのプライドを脇に置いていただければ、いろいろなことが見えてくると考えています。
勉強方法で何か困ったらご相談ください。応援しています。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2025年の土地家屋調査士鈴木修塾の開催予定
「事務所開業・経営」
2025年1月31日(金)13:30~2月2日(日)14:00
開業するには以下の3つの能力が必要です。
・業務処理能力
・業務受託能力
・事務所経営能力
業務処理能力は「土地業務」「建物業務」で教えますが、「業務受託」と「事務所経営」についてはここで教えます。
受講申し込み締め切りは令和7年1月10日(金)としますが、既にLINEによるグループ学習と、電話による個人学習が始まりました。参加ご希望の方はお早めに参加ください。
「土地業務」
5月15日(木)13:30~18日(日)14:00
土地業務については「裁判に耐えうる業務処理」が必要です。
先輩に質問して根拠法も調べずに、それらを踏襲しているだけでは、裁判に巻き込まれても対応できないし、そもそもお客様も守れません。
それらの観点で根拠法からしっかり教えますが、本来「裁判に巻き込まれない業務処理」が大事です。そこは重点的に教えます。
既に参加者希望者が数名います。
早めに登録していただければ、5月の集中講義を待たずに、申し込みの時点から電話で何をすれば良いかなど指導を始めたいと思います。参加ご希望の方はお早めに参加ください。
「建物業務」
2025年6月12日(木)13:30~6月15日(日)14:00
建物は土地に比べて甘く見られることが多いですが、意外と事故も結構あります。
決まったハウスメーカーの建物だけを1000棟登記しても経験値は1でしかありません。
依頼者の調査はそれで良いのですか。その書類に責任を持てますか。
建物業務で差を付けるノウハウを教えます。
既に参加希望者が数名になりました。
早めに登録していただければ、6月の集中講義を待たずに、申し込みの時点から電話で何をすれば良いかなど指導を始めたいと思います。参加ご希望の方はお早めに参加ください。
2025年の後期は皆さんのリクエストを見ながら開催を決めさせていただきます。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::